近年、メディアで関連書籍などがクローズアップされたことをきっかけにHSP(繊細過ぎて生きづらい人)の存在は広く認知されてきています。
それに伴って、これまであまり知られていなかった「ミソフォニア」という、音に対する特徴的な反応があることも、少しずつ認知が広まってきました。
今回は、ミソフォニアとはいったい何か、ミソフォニアの定義や特徴について当事者歴34年の専門家が解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
ミソフォニアの定義は?
特定の音を聞くことによって、非常に強い不快な感情を抱く反応のことが「ミソフォニア」だと定義されています。
特定の音が原因になる不快な感情のなかでも、とりわけ問題になるのは理不尽さをともなう憎悪感情です。
ミソフォニア当事者は、黒板を引っかいた時の「ギーッ」という音で感じるゾワゾワ感とは、全く違う感覚の不快感を訴えます。
そして「自分が出す音は気にならない」「他人が出す音だけに反応する」人が殆どで、ミソフォニアではない人がもっとも理解しづらく感じる特徴です。
ミソフォニアの語源は?
ミソフォニアとは、ラテン語で「音」を意味する「miso」と「嫌悪」を意味する「phonia」を組み合わせて作られた、いわゆる造語です。
2001年に、アメリカの研究者によってこの「ミソフォニア」という言葉が作られました。
日本語では、ミソフォニアのことを「音嫌悪症(おとけんおしょう)」もしくは「選択的音感受性症候群(せんたくてきおとかんじゅせいしょうこうぐん)」と呼ぶこともあります。
ひとことで説明すると、ミソフォニアって何?
ミソフォニアは、正常なはたらきの脳に備わっている機能のひとつ「条件反射」の一種です。
ミソフォニア研究が日本よりも進んでいるアメリカでは、当事者に対してMRIを使った脳の診断も行われています。
ところが脳や脳神経の異常は認められず、むしろ神経伝達機能の良い、正常な脳だという結論が出ています。
また、聴力に関しても、健常者との特徴的な違いは見受けられませんでした。
ミソフォニアの人の特徴は?精神病じゃないの?
HSP(敏感過ぎて疲れやすい人)の傾向は強めですが、それを除けばいわゆる健常者と比較して、むしろ特徴的な違いがないのが最大の特徴です。
そもそも現在、ミソフォニアは医学界において、精神病として正式に認められていません。
反対に、ミソフォニア当事者300人以上とダイレクトに対話してきた僕が知っている事実として、
- 職務遂行能力や学力
- 判断力、思考力
つまり、人間としての能力が、ミソフォニアではない人と何ら変わらないという事実を知っています。
- 医学的に精神病では「ない」とカテゴライズされている
- 仕事や勉強をする力は正常に備わっている
- コミュニケーション能力にも異常なし
これらの事実から、現段階ではミソフォニアを精神病扱いしない方が、適切な判断かと思います。
まとめると、ミソフォニア当事者は特定の音による深刻なストレスの悩みを抱えていますが、健常者と比較したとき、特徴的な違いは認められませんでした。
ミソフォニアになっている人の割合・人数は?
日本では大規模な調査が実施されていないので、アメリカで行われた、過去の調査データをもとに話します。
調査によって数字のバラつきは見られますが、対象者の10%〜20%の確率で、ミソフォニアの傾向が見受けられました。
これを日本の人口1億2,000万人に換算すると、およそ120万人〜240万人という割合で、ミソフォニアの人がいることになります。
実際に、当サイトのミソフォニア診断テストでは、1日平均300人、多い日だと7,000人以上もの人が診断テストを受けていますので、決して大げさな数字ではありません。
ミソフォニアを発症する年齢は?
これもアメリカでの統計調査がベースになりますが、成人するまでに50%がミソフォニアを発症しています。
とはいえ、50歳を過ぎてから症状を自覚・発見する人もいるので、どの年齢でもミソフォニアになる確率はあるということです。
ミソフォニアの人が苦手な音・反応する音は?
「繰り返すタイプの音」だという特徴がありますが、ミソフォニア当事者による個人差も大きく、じつにさまざまな音に対して反応します。
「ダメだ」という人の割合が圧倒的に多いのは、食べる時に出る咀嚼音です。
ミソフォニアのきっかけとなる音に関しては、別の記事に詳しくまとめましたので、こちらをご覧ください。
ミソフォニアと聴覚過敏は、具体的にどう違う?
「音に対して過敏な反応をする」という共通点のある、ミソフォニアと聴覚過敏。
具体的な違いについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、関心のある方はご覧ください。
ミソフォニアとHSPはどういう関係性がある?
ミソフォニア当事者のすべてがHSPではありませんが、ミソフォニアとHSPの関連性は強いです。
ざっくり言うと、「HSP」という大きなカテゴリーの中に、重複するかたちで「ミソフォニア」も存在します。
ミソフォニアとHSPの具体的な違いについては、こちらの記事にて詳しくまとめました。
まとめ
ミソフォニアに関しては未だに不確かな情報が飛び交っているので、現時点で明らかなことに絞り込んで解説しました。
図解つきで、具体的な17の対処法を詰め込んだミソフォニアの本も、ご興味あればぜひご一読を。
[kanren url=”https://misophonia.jp/mechanisms/”]
[kanren url=”https://misophonia.jp/misophonia-kazokudake/”]
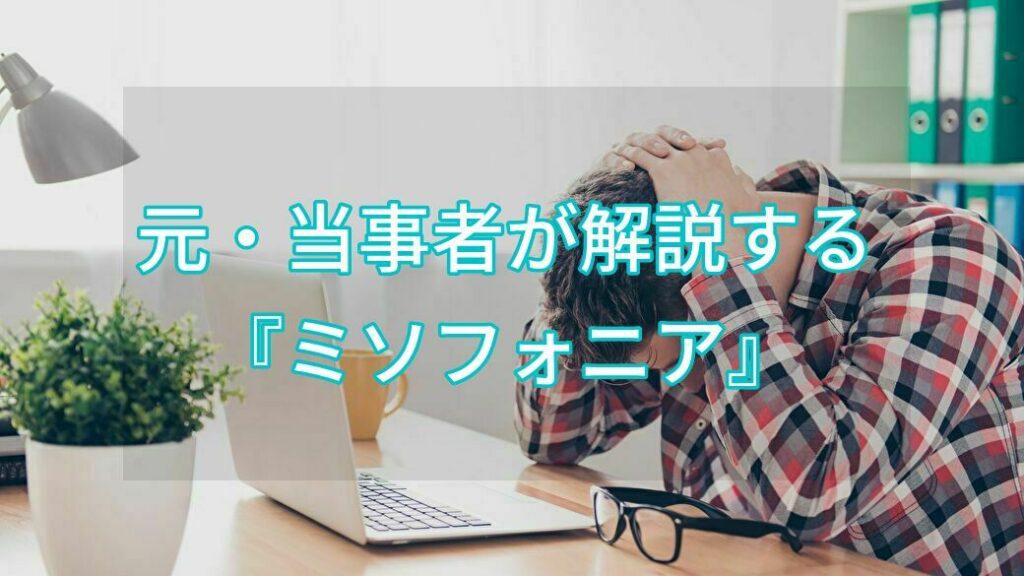

コメント