今回は、ミソフォニア当事者がやらざるを得ないことの多い「話し合い」についてお話ししようと思います。
話し合いのやり方を少し変えるだけで、親しい仲の人と疎遠になり、いずれ孤立してしまうのか、心の支えになり続けてくれるのか、全然違う結果に向かっていきます。
孤軍奮闘のしんどさで、心が折れてしまいたくない方には、今回の内容をぜひ知っていただきたいなと思います。
人生の損失が大きくなっていく、溝を深める話し合い
[aside type=”boader”]「感情×理屈」で相手の過ちを責める[/aside]
音の問題以外で話し合いをした場合でも、これをやってしまうと話し合いそのものが決裂してしまいます。
相手が「聞く耳を持とう」と思える理屈は、あなたの中でどういうことがあって、こうなっていって、こういう風になったという客観的な状況説明だけです。
「あなたのせいでこうなった」系の責め文句は、言いたくなる気持ちはわかりますが、誰のためにもならないので、自分の未来のためにやめておきましょう。
[aside type=”boader”]「普通」や「常識」を多用した決めつけ[/aside]
話し合いをする前に、「普通こうだよね」や「常識的に」といった言葉をお互いに使わないというルールを決めておくことをおすすめします。
そもそも、あなたが普通や常識の枠の中で幸せになり得ない状態だからこそ、もめてしまうわけです。
同じような不快な経験を繰り返したくないのは、あなたにとっても、相手にとっても同じなので、「予測のできない事故が起こってしまった」くらいの自己認識にしておくと、感情のエスカレートも止めやすくなります。
[aside type=”boader”]「自分は間違っていない」の頑なな主張[/aside]
自分にとっての「正しさ」を押し付けるような方向に向かう主張は、相手が心を閉ざしてしまう原因になります。
どちらが良い悪いではなく、[aside type=”boader”]なんなら自分が悪いでも構わない。それで構わないから、この先同じようなことが起こらないように、どうしていこう?[/aside]が話し合いの焦点だと、ブラさない意識が必要です。
「またおんなじことの繰り返し…」から抜け出せる、生産的な話し合い
[aside type=”boader”]相手が「こう思う」と言っていることを否定しない[/aside]
話し合いが決裂する一番の原因は、お互いが自発的に思うこと、つまり事実の否定です。
自分と、相手が思うことに違いがあるのは当たり前で、認識のすれ違いがあるからこそ話し合いの必要性が出ています。
相手にも自分の意思があるので、「こういう風に思う」と言っている事は事実なわけですから、お互いの自由意志に対して善悪のジャッジを下さない、これが大事です。
[aside type=”boader”]相手の行動よりも、自分の行動の変化を優先[/aside]
もしもあなたに非がなかったとしても[aside type=”boader”]「自分は何も変えるつもりはないから、あなただけが行動を改めて」[/aside]と言われて、不服を感じずに従ってくれる人はいません。
[aside type=”boader”]
相手が変わってくれるかどうかはわからない。
たとえ相手が変わってくれなかったとしても、同じようなことが起こらないように、自分の行動には何か改善を加えよう。
[/aside]
こういった前提を持ちながら話し合いをすると、同じことの繰り返しから脱却しやすくなります。
[aside type=”boader”]取り戻せない過去に執着せず「先に許す」を徹底[/aside]
自分に落ち度があってもなくても、音の問題で相手に「いついかなる時も失敗してはダメ」を約束させること自体が、とても酷なことです。
よくあるのが「あの時はごめん。でもね、あなただって〜」と謝った直後にすかざず言い訳をつなげる、もしくは自分の正当性を述べるというケースですが、やめておきましょう。
こういう「謝ってない謝罪」は理不尽の押し付け合いになるだけです。
ケースバイケースの対応が必要なので、テンプレートがあるわけではありませんが、一例をあげておきますね。
[aside type=”boader”]
自分のこういうところが良くなかったと思うから、これからはそうならないためにこうしようと思う。
これでいいのか確信が持てないから、あなたの考えていることも聞かせてほしい。
[/aside]
こういった「自己改善の意思を伝える→相手の意見を聞く」という話の持ち出し方をすれば、生産的な話し合いに向かいやすくなります。
まとめ
相互理解のために話し合いをする時、議論ではなく対話の方向へ持っていこうという意識を忘れないことが大切です。
既に議論が起こっている、つまりあなたの「こうしたい」と相手の「こうしたい」がぶつかりあってしまっているからこそ、話し合いが必要になっています。
お互いに居心地の悪い、ぎくしゃくとした溝を深めないためには、「これから先どうしていこうか」をお互いの納得を得ることありきで考えていく、というスタンスを崩さないようにしましょう。
実際問題、あなたが孤立を強めれば強めるほど、ミソフォニアの悩みを良くしていく事は難しくなります。
克服に必要なプロセスとして、精神的にかなりきついシーンを乗り切っていくしかない時が、今後何度も訪れます。
(乗り越えれば貴重な教訓を得られるので、自己成長のチャンスです!)
なので心の支えになってくれて、見守ってくれる意思がある人を突き放してしまわないように、主張のぶつけ合いではなく、相互理解のベクトルへ向けていく意識を、忘れないようにしましょう。
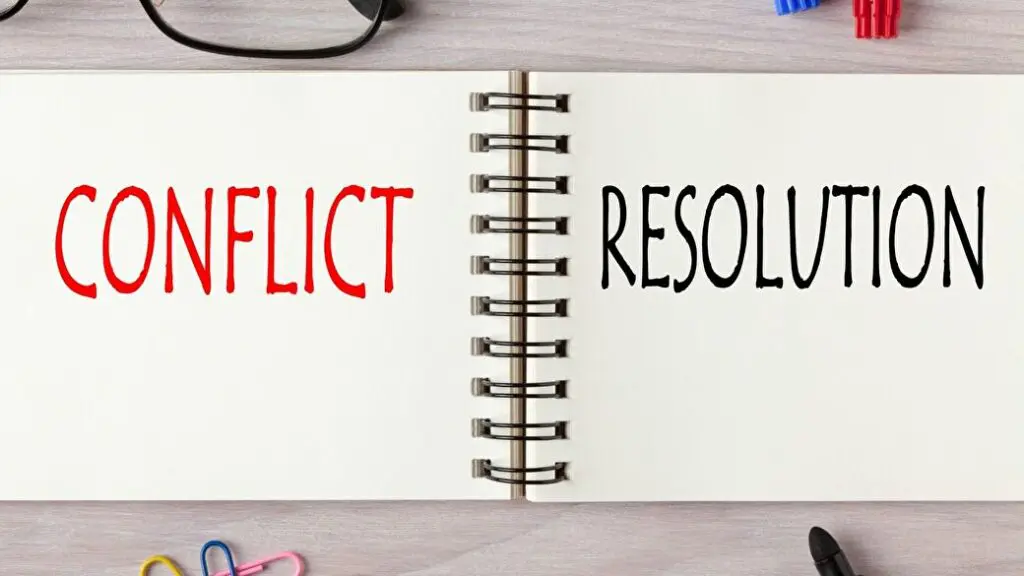


コメント